8月15日金曜日に公開予定の動画は、通常のダイアログ回ではなく、 [Someone’s Insight]といってレッスンのテーマに沿ったインタビュー回の第1回目です。
今回は、特別企画として“Someone’s Insight”。
25年にわたり中国ビジネスの現場で活躍してきたゲストに、「今、ビジネスパーソンが本当に知っておくべき現実」や「未来へのヒント」について、リアルな声で語っていただきます。
政治リスク、消費者の変化、現地パートナーとの付き合い方――教科書には載らない、“生きた経験則”が満載です。
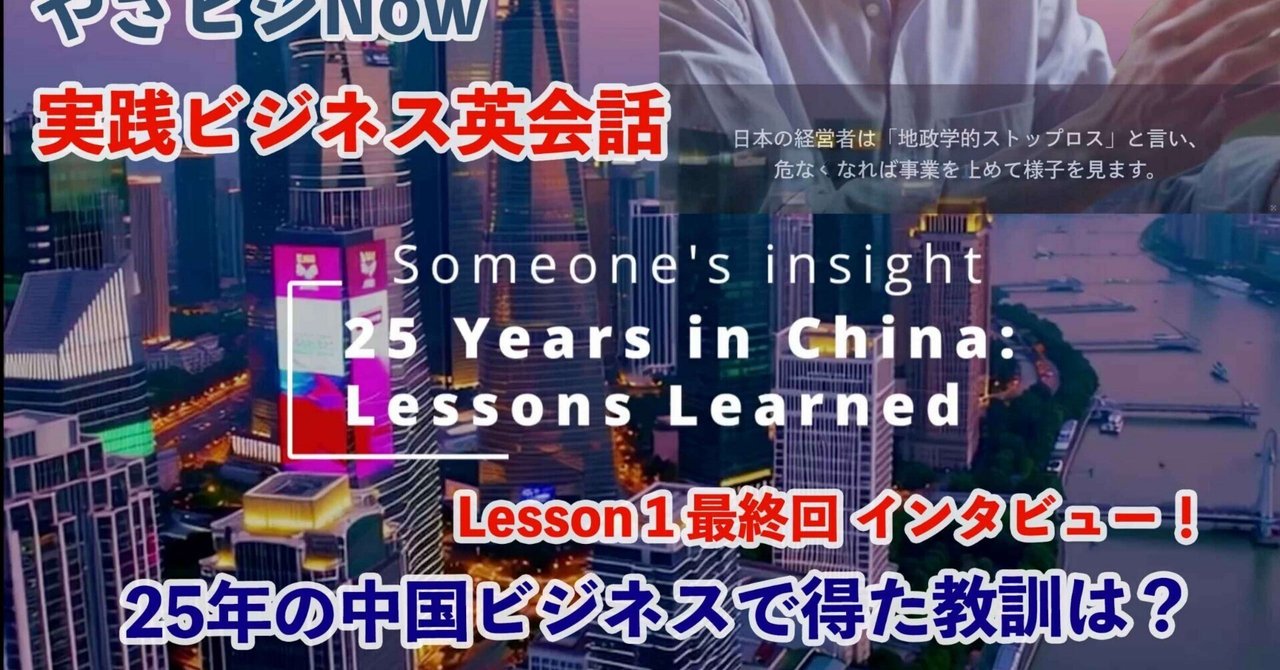
*の付いた事項は制度・統計・情勢の変動が早く、年や情報源によって数値・運用が変わる可能性があります(ブログ掲載時は最新の一次情報で点検を推奨)。
25年の中国ビジネスで得た教訓は?
中国での25年を経て、何が本当に変わり、何が今も重要なのか——よく聞かれます。私の出発点は2000年、深圳のホテルでWTO加盟関連の草案を翻訳していた頃。そこにいるだけで“ゲームチェンジ”を感じました。いまは、クライアントのESGデータ基盤を整え、越境コンプライアンスに取り組んでいます。
ここでは、現場でよく受ける問いに沿って話を進めます。「今でも中国は“行く価値”があるのか?」「地政学は損益にどう効く?」「2025年の“本当の顧客”は誰?」「どこに張るべきか?」そして「この二十数年の学びで、何が今も通用するのか?」です。
「規制が増えた今でも、中国進出は割に合うのか?」
結論はイエス。ただし“計算式”は変わりました。20年前は「安い労働力と二桁成長」でしたが、2025年は「約4億人の中間層」「最先端のデジタル基盤」「政府によるグリーン/ハイテク投資」* がカギ。利幅は薄く、回収は長期化しがちです。
目安となる数字は3つ――実質成長率5%、対中FDIは前年▲13.7%、人口の約70%が下位都市(*統計は年によって変動)。成長はあるが、資本はより選別的になり、購買力は広く分散している。
勝ち筋はだいたい三つ:①現地勢が埋めにくいイノベーション・ニッチ(例:先端医療機器)、②小売で競るのではなく中国のエコシステムに深く“組む”、③カーボンピークや高齢化対策など政策の追い風にぴったり合わせる。どれにも当てはまらないなら、コストがリターンを上回るでしょう。
「日中の政治的緊張はビジネスにどう影響する?」
地政学は読みにくい向かい風として“価格に織り込む”対象です。2012年の領土問題の際、日本車の販売は6週間で約半減、その翌年に持ち直しました (*出来事・数値は要確認)。これは、経済の力が怒りに勝ることもあるが、それは火が冷めてからの話だということを示している。
今日のリスク構造はより複雑だ。東京は輸出規制でワシントンと足並みをそろえ、一方で北京は遅延や検査で対抗し、規制の霧を生み出している。日本の経営幹部たちは今や地政学的な「ストップロス」について語るようになった。つまり、世論が悪化すればキャンペーンを中断し、サプライチェーンを迂回させ、状況が落ち着くまで待つということだ。
それでも中国の消費者は、日本の職人技――スキンケア、工具、高級食品――を評価している。鍵は、自己主張を抑えたローカライズだ。旗もスローガンも掲げず、地域社会との関わりと静かな品質を打ち出す。そして必ず、ベトナムや九州に「プランB」の倉庫を確保しておくことだ。(*地政学・制度は変化しやすい)。
「2025年の中国消費者と都市階層は?」
3つの波が重なっている様子を思い描いてほしい。
第1の波はティア1の巨大都市――北京、上海、深圳。時間に追われ、健康志向が強く、ESG意識も非常に高い。豆がゼロカーボン農園由来であれば、60元のナイトロコールドブリューでも喜んで払うだろう。
第2の波はティア2・ティア3の成長層――成都、南京、合肥といった都市だ。住宅は安く、所得の伸びは速い。年収14万元の家庭でも消費に約80%を費やす。共同購入アプリやライブコマースが主要な発見チャネルになっている。
第3の波は低位都市の飛び級組。小さな町でも5Gと即時配送が隅々まで行き渡り、彼らにとって初めての海外ブランド体験は、72時間以内に届く20ユーロの越境バンドルであることが多い。
すべての層に共通して、Z世代は愛国的で、かつ新しいもの好きだ。日本製のコラーゲンパウダーも試すだろうが、それは柚子味で、パッケージに中国語のミームが入っていることが条件だ。
「地元勢が強い中で、外資はどこで勝てる?」
外国企業が勝つことはできるが、真正面から価格競争をしてはいけない。アリババはアマゾンを打ち負かし、BYDはトヨタのハイブリッドを上回る販売をしている。地元企業はホームグラウンドの優位性、政策の後押し、そして価格やスピードの面で強みを持っている。
では、何がより有効か?
「つるはしとスコップ」を売ること――EV工場で使われるドイツ製ロボットアーム、乳業向けのスイス製フレーバー酵素、半導体工場でのオランダ製チップ製造装置などだ。
あるいは超プレミアム路線――Apple、LVMH、資生堂はいまだに世界的なステータスと安全な品質の象徴だ。
もう一つの方法は、共同知的財産――技術を共同開発し、パートナーにマーケティングを任せ、自分はロイヤリティを受け取るやり方だ。Pinduoduoの次を目指すのは愚の骨頂。しかし、あらゆるベストセラーに欠かせない「隠れた成分」になることは――まさに金の粉である。
「2025–2030で伸びる業種は?」
勝者は、政策資金と社会の痛点を追う。グリーンテックは巨大市場だ――中国は2060年までにネットゼロを目指しており、バッテリー、リサイクル、水素などあらゆる分野に補助金が注がれている。
高齢者ケアと健康分野――これは大きい。2035年までに、中国人の4人に1人が60歳以上になる。日本は高齢者向け機器、低ナトリウム食品、老人ホーム設計で優位性を持つ。
アグリテック?食料安全保障は国家的な執念だ。環境制御型農業、種子遺伝子、コールドチェーン物流――外国資本規制があっても歓迎される。
産業自動化――賃金が上昇し、工場は高度化している。日本製サーボモーターはいまだにトップだ。
プロフェッショナルサービスと知財マネタイズ――コンサルティング、リスク管理、ESG監査など。世界展開する中国企業には、そのグローバルな洗練が必要だ。
ただし注意点として、クラウドや消費者向けインターネットは準閉鎖的であり、ビッグデータツールは精査を受ける。リスクが高すぎる。
「25年の経験からの教訓」
私には3つ、いや、4つの生存ルールがある。
1 | コンプライアンスのデジタル化 ―― 宴席での握手は許可証ではない。SAMR(国家市場監督管理総局)への届出をリアルタイムで追えるダッシュボードこそが本当の資産だ。
2 | 謙虚なローカライズ ―― 単なる翻訳ではない。アイコン、色、プラグの形状まで入れ替える。不安なら午前3時の抖音(Douyin)でテストを――最高のライブ型フォーカスグループになる。
3 | すべてを数値化 ―― 愛国心はスローガンで論争できるが、ハードデータには逆らえない。不良率、研修時間、削減した炭素量――数字は雄弁だ。
4 | オプションを確保 ―― ASEANへのバックアップ、危機時のPR台本、現金の備蓄。中国は忍耐を報い、慢心を罰する。
25年の結論
20年を経ての結論――中国は「避けられないが、決して単純ではない」。迷路であり、ときにトランポリンでもある。即席の成功?ほぼない。長期的な学習ラボとして扱えば、地域全体への展開拠点になり得る。
日本企業は「光」と「影」の両方を背負う。精密さは強み、歴史は重荷。だから――データを持ち、敬意を示し、バックアッププランを常に持つべきだ。
最後のヒント:ポートフォリオ思考を持て。グリーンテックに1枚、アフターサービスに1枚、そしてムーンショットに1枚賭ける。国家の優先事項に沿い、現地人材を育て、謙虚であり続ける。
そうすれば、扉は開き続ける――狭くはあるが、開いたままだ。
聞いてくれてありがとう。好奇心と適応力を持ち続けて。次の中国市場取締役会レビュー、一発合格を祈る。
Key Vocabulary
- WTO accession:WTO加盟手続き
- ESG data pipeline:ESGデータの収集・整備・可視化の流れ
- cross-border compliance:越境コンプライアンス対応
- middle class (≈400 million):中間層(約4億人規模)🟡推計幅あり
- lower-tier cities:下位都市(県級・地級など)
- innovation niche:現地勢が埋めにくい技術ニッチ
- policy tailwinds:政策の追い風(重点分野との整合)
- regulatory fog:規制の“霧”、不確実な審査・遅延
- consumer sentiment:消費者感情
- low-ego localization:低エゴなローカライズ(出しゃばらず現地目線)
- geopolitical stop-loss:地政学的ストップロス(撤退・一時停止の基準)
- live-stream commerce:ライブコマース
- picks and shovels strategy:“ツルハシ・スコップ”戦略(装置・部材・基盤を売る)
- ultra-premium positioning:超プレミアムの位置取り
- joint IP / co-develop tech:共同知財・技術共創
- royalty model:ロイヤルティ収益モデル
- carbon peaking / net-zero:炭素排出ピークアウト/ネットゼロ
- elderly care:高齢者ケア(介護・シニア向けヘルス)
- controlled-environment farming:閉鎖型(環境制御)農業
- cold-chain logistics:コールドチェーン物流
- industrial automation:産業自動化(FA、ロボット等)
- servo motors:サーボモーター
- professional services:専門サービス(コンサル、リスク、ESG監査)
- IP monetization:知財の収益化
- SAMR filings:市場監督総局(SAMR)への各種届出 🟡制度運用は改定あり
- digitize compliance:法令順守の“常時監視・可視化”
- live focus group (on Douyin):抖音での即席ユーザー検証
- quantify everything:全指標の定量化
- optionality:選択肢・退路を持つ設計
- portfolio thinking:ポートフォリオ発想(分散して張る)
- moonshot:ムーンショット(大きな賭け・高リスク高リターン)
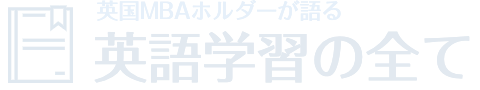

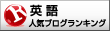

コメント