以前、英文法の基礎がない人には「英文法講義の実況中継」という本を勧めたいという記事を書いた。

実際、大学受験レベルの知識があればTOEICのPart5に出てくるような英文法は難しくないのではないかと思う。
しかし今回は「もうTOEICのスコア表の<英文法が理解できる>の項目はほとんど100%かそれに近いのを取っているよ」という人に、より英語のセンスを養える本を紹介したいと思う。
Intermediate(中級)だが、ある程度のレベルでもかなり学びがある
自分はこれはTOEICでいうと800点を超えた頃に使い始めたが、文法の理解度に関してはほぼほぼ100%だった。
割と文法に関しては自信があったのだが、ふとしたきっかけでこのGrammar in useの存在を知り、英語で書かれた英文法解説というものに興味があったので始めてみた。
その頃になると英語の勉強時間として切り分けている間は自分の頭の中に日本語を介在させたくない、というような気持ちがあり、これならちょうど良いと思ったのだ。
しかし最初の方の項目で既に「そうだったのか!」と眼から鱗が落ちるようなことが多く、かなり勉強になったし今でもあの本で学んだことを意識して英文を書いていることも多い。
例えば、最初はI’m doingとI doの話から入る。「こんなの簡単だよ!」と思うかもしれない。
でも、例えばこんな項目がある。
I always do and I’m always doing
これについて、こんな風に解説されている。
大抵は’I always do something’ (= I do it every time) を使う。
例えば、 I always go to work by car.とは言うが、I’m always goingとは言わない。
しかし、I’m always doing somethingと言える時もあり、その場合は少し違う意味になってくる。
例えば、”I’ve lost my key again. I’m always losing things.”と言う場合、それは常に何かをなくしているということではない。ただ、あまりにも頻繁に、普通よりも頻繁に何かを無くしている、という意味になる。
You’re always -ing というのは、話し手が「普通」と思うよりも頻繁にyouがその行為をしているということになる。
例として、
You’re always watching television. You should do something more active.
John is never satisfied. He’s always complaining.
こういう例文がついているので、日本語で言うなら「あなたはいっつもテレビばっかり見てる」とか「彼はいっつも文句ばっかり言ってる」という感じがわかってくる。
また、I will doとI’m going to do の違いの項もある。自分の知る限り、多くの日本の中学校ではこれを同じとして教えているのではないだろうか。
日本にいながらにして語学留学の授業を受けているようなもの
自分は大学時代の3週間の研修を除けば、英語の語学留学というものはしたことがないのだが、別のヨーロッパ言語の語学学校にはいくつか通ったので、語学留学ビザで住んでいたわけではないが語学学校での教え方というものはわかっている。
その言語で、こういう風にいろんな用法を比較しながら教えられる。そうした語学学校の経験を経て、改めてこの本を読んでみると、まさに語学学校のような感じで項目が進んでいる感じがする。
説明1ページ、練習問題1ページという形式
ただ素直に説明を読み、練習問題に取り組む、ということをやっているだけで、かなり定着するようにできている。
ただ、練習問題を解く、というのはそれなりに勉強態勢になっていないとできないし、少し時間もかかるので、時間がない人はとりあえず一読してみてもいいかもしれない。
というのは自分は几帳面に読んで解いて、とやっていたら他の勉強もあるため、仕事の後に毎日コツコツやるまでに至らず、やっては1週間空き、また再開して…となり、終わらせるのに1年かかってしまったからだ。
とりあえず最初にどんどん読み進めてみるというのもやり方の一つだと思う。
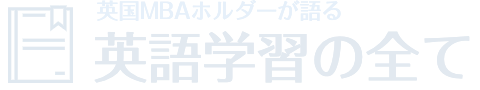


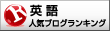
コメント